最近、「『写真作品』とは」みたいなことをよく考えます。
みなさんこんにちは。
イメージングディレクター/フォトグラファーの芳田賢明(よしだ たかあき)です。
ラジオのレギュラー番組だと思っていろいろ書いてみる、連載「memorygram」第17回です。
商業写真の制作を毎日していると、クリエーターとしての自分と作家としての自分のバランスが取れなくなってきて、定期的に商業ベースでない「作品」としての写真に触れる、あるいは生み出すことを渇望するようになります。
ただ最近は、「作品」というものについて、「商業写真でない写真」という意味を超えて、「写真作品とは何か」ということを考えています。
「商業写真」と「写真作品」、私の中ではこの両者ははっきりと区別していて、どちらも同じ「写真」ではありますが、そのアプローチと考え方は正反対です。
これまで私の中では、簡単に言うと商業写真は「他者を幸せにすることが最優先」で、写真作品は「自己を幸せにすることが最優先」という区別をしていました。
商業写真にはクライアント(発注者)がいて、そのクライアントが設定する目的(商品を知ってもらうためとか、より売れるようにとか)を達成することが求められます。撮影者が自分の満足のために撮りたいものを好きに撮れば良いわけではなく、あくまでクライアントが求めるものを撮る必要があります。
一方、写真作品は「自己表現」が全てですから、少なくとも発表するまでは自己完結の写真です。自分が表現したいことや伝えたいこと、見せたいことを写真に顕すことができれば、ひとまず成立するはずです。
私は美術系の学校を出て商業写真制作の仕事に就きましたが、基本的に学校の実習は「作品制作」です。それは課題によって商業美術の場合も芸術作品の場合もありますが、いずれにしても中心は自分で、クライアントありきという仕事上の感覚はそこまでないはずです。
そのため、美術系の学校から制作の仕事に就いた人の多くは、想像していた仕事像と現実との大きなギャップを就職後に感じます。
私の場合、会社に入って5年程度でその本質に気づき、さらに仕事を続ける中で先に書いたような明確な線引きができるようになりましたが、そこに気づくまでは苦しい日々になります。
また、線引きしているとはいえ、仕事で商業物を制作しながらプライベートで作品をつくっていると、その相互が影響し合うことになります。プライベートでの制作経験が仕事に良い影響を与え、仕事での経験が作品に深みを与えるような形であれば良いですが、仕事での制作に自分を出しすぎればクレームとして返ってきますし、思考や感覚が商業に染まりすぎると、「自分の作品って何だっけ」というところまで行ってしまいかねません。
これはフォトグラファーに限らず、デザイナーや作曲家など、保有する技術によって商業制作物も作品も生み出せる人になら存在する葛藤だと思います。
「写真作品とは何か」を深く考えるようになったのは、複数の専門家から「あなたのポートレートはモデルに撮らされている。あなたがモデルを撮っているわけじゃない」と言われたことからです。
その言葉を一人ではなく複数から受けたこともあり、何が正しいのかよくわからなくなってしまいました。
私としては、指摘の通り撮らされている感覚で撮っているのです。人は誰にも魅力的な部分があり、そこを引き出すのがフォトグラファーである──溢れ出てくる魅力を受け止める=掴むのではなく掬う、そんなイメージで撮っています。それが良くないとはどういうことなのか。
しかし、いろいろ考えていく中で気づきます。写真を始めた頃から撮り続けている都市のスナップは、「都市から溢れ出てくる魅力を掬う」という感覚で撮っているだろうか。確かに幾らかはそういう割合もあるけれど、どちらかというと「自分を都市に投影している」ことに──なるほど、街の写真は自分のために撮っているけれど、ポートレートは人のために撮っているのだ。
そうして、「写真作品というのは被写体に撮らされるものではなく、被写体に自分を写すことなのかもしれない」と思ったのです。
先日東京都美術館で観た「ハマスホイとデンマーク絵画」展から得た刺激も大きかったです。
空間が物語るもの、後姿が物語るもの。そこに込められた感情。
作品を謳うならば、もっと一枚一枚を丁寧に撮るべきなのではないか──。
写真は他の芸術と違い、物理的にはどう頑張っても「そこにあるもの」を写し取ることしかできません。場面の演出や被写体に演技をつけることはできても、現実に存在しないものは画像にできません。その特性は、写真の特殊性として極めて大きいものがあると思います。言わずもがな、CGなどを使えばフォトライクな嘘を現実に溶け込ますことができますが、それは写真ではなくCGであるわけで。
自ら筆を走らせない限り描けない、あるいは自ら編まなければ生み出せないといったものではなく、ボタンを押せば写ってしまうという事実には、そこに「自分」を写し込ませることの難しさがはらんでいると思います。
「そこにある現実」をただ写し、自分の色で仕立て上げることで「自分の作品だ」と思ってしまうことの安易さに反省をしなければならないのかもしれない──そういった安易な表現に対し「それは本当に作品か」という疑問が生まれるのです。
私が撮る写真は、RAW現像にこだわり、独自のトーンと色味で表現しています。それが作風の一つだと思っているし、そこには自信があります。そしてそれは銀塩写真における暗室作業と同じことだと思っています。
ただ、どんなに暗室作業が優れていたとしても、写真そのものが優れていなければ意味がない。本当に良い写真は、きっとベタ焼きの時点から良いし、撮りっぱなしのJPEGでも良いはずであるということを肝に銘じています。仕上げに自信があるのならなおさら、そこに甘えてはいけない、と。
だからこれまでも、光線と影と陰、構図や被写界深度、そういったことには自分なりにこだわってきました。でもそれは、どちらかというとテクニカルな話かもしれません。
もっと根源的な、「自分を表現する手段として、音楽でも文字でも絵でもなく写真を選んでいる」ということ。そして、「自分を写真に写す。その被写体が自分でなかったとしても、そこに自分自身が写っている」ということを、これまで真剣に考えたことがあっただろうか。
リコーGRを再び買ったのは、実はそんな自問自答の末の選択でした。
自分の生活の中に、その生活を写し取るカメラを再び埋め込むことによって、自分自身を写すということに向き合えるのではないか、と。
しかしそう簡単にはいきませんでした。自分にとって自分の日常生活とは、あまりに無味乾燥なのです。
「日常生活への憧れ」──そんな言葉が、このところ自分の作品テーマのフレーズとして浮かび上がっています。
──本当はなりたいけれどなれない誰かの生活、その憧れを、自分の写真の中だけでも叶える。そしてその裏には、叶うことのない自分自身の姿が写っている。そんな写真。
──今撮らなければならないのは、いや、一生かけて撮ることになるだろう根源的なテーマは、おそらくそれなのだと。
結局、memorygramのさらに深部にある真実は、「孤独」であり「劣等感」なのでしょう。
写真にしても音楽にしても小説にしても、これまでやってきた表現活動は全てそこから生み出されているのです。
今の自分にとってどういう方法、どういう手段が良いのか。その答えはまだ出せていません。
そこにあるものしか写らない、ストレートに思いを描けない。写真は難しいです。
本当に難しい、と、ようやく気づいたところです。
【プロフィール】
芳田 賢明(よしだ たかあき)
イメージングディレクター/フォトグラファー。
「クオリティの高い撮影・RAW現像で、良い写真を楽につくる」をテーマに写真制作ディレクションを行っている。撮影ではポートレートや舞台裏のオフショット撮影を得意とする。
Webサイト…https://atmai.net/
Instagram…https://www.instagram.com/takaaki_yoshida_/

芳田賢明 著、プロカメラマンに向けた[仕事に即役立つ本]
「誰も教えてくれなかった デジタル時代の写真づくり」
好評発売中
(honto)
https://honto.jp/netstore/pd-book_29714615.html
(ヨドバシ・ドット・コム)
https://www.yodobashi.com/product/100000009003153309/
(Amazon)
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4870852349/











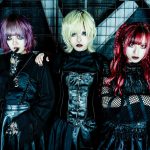











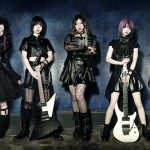



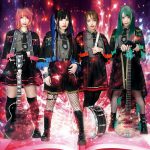





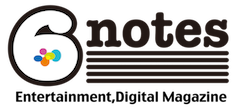
この記事へのコメントはありません。