『story part.2』
高速道路を降りてから、一旦、一般道を通って海沿いの有料道路に入った。
自動車専用道なのだが、しばらくの間は一般道のと同じような海沿いの山道が続く。
残念ながら雨足は一向に弱る気配はなかった。
しばらく道なりに進んでいくと大型のレストハウスがあった。
そこに車を入れて一度休憩することにする。
雨のせいなのか普段はあふれる程の駐車場も、車の数はさほど多くなかった。
レストルームに立ち寄ってから自動販売機のカップの珈琲を買った。
外の気温がやはり普段より寒かったのか、カップの中の珈琲が妙に熱く感じる。
程なくして彼女がやってきた。
「あっ、美味しそう。私も飲もうかな」
「どれがいい?」
「う〜んとね…」
しばらく考えて
「これにする」
と、彼女はフレーバーの紅茶を選んだ。
カップのドリンクを買ってあげると、少しはにかんだように
「ありがと」
と呟いた。
窓の外の景色は相変わらずの雨模様だ。
2人でカップの熱いドリンクをゆっくり飲みながら、何とも言えない気持ちも飲み込んで景色を眺めた。
「とりあえず…」
なんとか雰囲気を変えたかったが、不器用なので上手く気持ちを表現できない。
「目的地まで行ってみようか」
「うん!」
想像と違う、明るい表情でうなずいた彼女。
またもやドキッとしてしまう。
こんな時のリアクションはどうすればいいのか…。
ついドギマギした表情になってしまった。
そんな僕を見て、彼女は笑顔でそっと目をそらした。
レストハウスの中を一通り歩きながら土産物などを見ながら、彼女の好みをさりげなく聞いてみた。
レジカウンターの前を通りかかると、小さなぬいぐるみがいろいろと置いてあった。
「あ〜、可愛い!」
彼女が手にしたのは小さな熊のアクセサリーサイズのぬいぐるみだった。
「へぇ、こういうの好きなんだ」
「だって、可愛いじゃない」
「そうだね」
「本当にそう思ってる?」
ちょっと膨れたような態度が、見たことのない彼女の表情を見られて嬉しかった。
今度はこちらのそんな気持ちを見透かされないように気を付ける。
「じゃあ、今日の記念に買ってあげるよ」
「えっ、ホントに?」
「ささやかなプレゼントだけどね」
「嬉しい! 雨のドライブの記念だね」
痛いところを突かれたが、それもまあ、思い出になればいい。
雨に打たれながら急ぎ足で車に戻る。
目的の場所までは、もうそれほど遠くない。
車のエンジンをかける。
タイヤが路面にたまった雨水を撥ね上げる。
道路の本線に戻った。車の数はやはり多くない。
何度も通った事のある馴染みの道だが、彼女が隣にいるのでいつものような気持ちとは一味違う。
彼女と初めてのドライブなので、自分の一番好きな道を一緒に走りたかった。
しかし、想定外の雨に翻弄されているばかりだ。
そんな気持ちを知ってか知らずか、カーステレオはボニー・タイラーの「Total Eclipse Of The Heart」を歌う。
「なんだか悲しい感じがするけど、それだけじゃないような雰囲気」
「…うっ、鋭いかも」
「切ない旋律なのに、その裏にある力強さを感じる…」
「すごいね。この曲、聴いたことある?」
「ううん、初めて聴いた。でも、なんだか切なく訴えてくる感じだね」
真っ直ぐ前を見つめたまま彼女が言った。
「歌詞が分かる?」
「まさか、分からないよ。でもこの人の歌から伝わってくるよ、そんな感じが」
「ほほう…大した洞察力だな」
「そうなの?」
「歌詞の対訳を読んだけど、なかなか一筋縄ではいかない心の葛藤みたいな内容だったよ」
「じゃあ、イメージした通りだね」
「まさにそんな感じだよ」
少しづつ、心の緊張がほぐれてきたような気がした。
彼女も勿論だが自分もそうだった。
どちらかと言えば、自分の方が緊張していることに気付いていた。
この曲が響き渡る車の室内は、なにか荘厳な響きが通り過ぎた後のようになっている。
ちょっと雰囲気を戻さないと、クールなムードになってしまう。
ダッシュボードの中から別のカセットを取り出したい。
ダッシュボードを指さして彼女に伝える。
「そこの中から別のカセットを出してくれる」
「ここ?」
ダッシュボードを彼女は開けた。
インデックスを書いたカセットが並んでいる。
「どれがいいの?」
「セレクト2って奴を出して」
「セレクト…あっ、あった」
今、廻しているカセットをカーステレオのデッキから取り出して彼女に渡す。
「空のケースがあるから入れていおいて」
「はい」
彼女は別のカセットテープをケースから取り出して渡してくれた。
それを僕はデッキの中にセットした。
カセットの頭のローディングが終わると、車内に汽笛の音が二つ鳴り響いた。
1曲目はビリー・ジョエルの「Allentown」が始まった。
車は綺麗に舗装された広めの道に入った。
ここからは左手にずっと海の大パノラマが続く。
この道中で特に好きなエリアに入った。
太平洋からやって来た波が割と元気よくこちらに向かってきては飛沫をはね上げている。
前も後ろもかなり離れた位置にしか走行車両はいなかった。
ゆったりと走っても気兼ねすることはない。
これが晴れた景色だったら…彼女もはしゃいでいただろう思うと、やはり残念な気持ちになってしまう。
心の中では「次は天気のいい日に来ようね」というセリフがグルグルと渦巻いているのだが、その言葉が言い出せずに目的地に到着しそうだ。
有料道路の降り口の看板が見えてきた。
ゆっくりと右にカーブすると左右に分かれる突き当りの信号がある。
車を停止させて左にウィンカーを出す。
「目的地に着いたの?」
彼女が辺りを見回しながら聞いた。
「うん。もうすぐゴールに到着」
信号が変わって車を進める。
海岸線の遊歩道沿いに真っ直ぐ進む。
しばらく進んで海岸沿いのパーキングに車を入れた。
パーキングに車の数はまばらだ。
真ん中あたりの場所に頭を海岸に向けて車を停めた。
車のエンジンを止めると室内に雨の音が広がった。
彼女はバックシートに置いてあった、籐で出来たバスケットを取った。
はにかむような表情でバスケットの蓋を開ける。
中には可愛らしいランチが色とりどりに綺麗に収まっていた。
ポットを取り出してカップに紅茶を入れて渡してくれた。
まだ十分に暖かい紅茶から白い湯気が漂う。
「ありがとう、凄いね。作ってくれたんだ」
「うん。早起きして頑張っちゃった」
「いや、なんだかカンドーしちゃった」
「うふふ、そうなんだ。嬉しい」
彼女はバスケットからサンドウィッチやおかずを取り分ける。
差し出されたランチをゆっくりと食べた。
フロントグラスには雨のスクリーンがゆがみながら流れ続けていて、その向こうに砂浜が静かにぼやけて見える。
ランチはとても美味しかった。
彼女は紅茶が好きなのだなというのが分かる、優しい味わいだった。
せっかく作って持ってきてくれたのに、自動販売機のカップティーを飲ませてしまった事が悔しい。
カーステレオからブルース・ホーンズビー&ザ・レインジの「マンドリン・レイン」が流れ出した。
2人は黙ったまま曲を聴きいった。
彼は歌う「聞いてごらんマンドリンのような雨音を」
今のシチュエイションにはハマりすぎた曲だ。
このままではいけない…意を決して僕は言った。
「今日はあいにくの雨になっちゃったけど…でもドライブが出来てすごく嬉しくて…」
頭では分かっているつもりでも上手く言葉にすることが出来ないでいると…
「うん、ありがとう。雨も嫌いじゃないけど、晴れていたらもっと素敵な景色がみれただろうね」
「そうなんだよ、だからさ…また…」
「また…連れてきてくれる?」
「…もちろん」
「よかった。今日は雨の景色を眺めながら、ゆっくり帰ろうね」
彼女の言葉は僕をオブラートにくるむように優しく感じた。
雨はまだやむことなく降り続けている。
車のエンジンをかけてワイパーを動かすと、急に目の前の景色がハッキリとして、不思議な空間から戻ってきたような気がした。
車をバックで切り返して、出口に向かって発進した。
end.
前回と今回はいつもと違う切り口でお送りしました。
このお話のベースになっているのは、自分が少年時代にドライブデートに想いを寄せるきっかけになった憧れのシチュエイションの曲です。
松田聖子さんの3rdアルバム「風立ちぬ」の収録曲「雨のリゾート」です。
この曲の作詞は心の師である松本隆先生。
自分が作詞活動を始めようと思う、きっかけの曲だったかもしれません。
短いセンテンスの中にイメージする世界観に、初めてハッキリと出会った曲でありました。
主人公はドライブをしている女の子なのですが、少しのヒントで女の子の心情が見事に伝わってきます。
それがまた、切なくもキュートな訳ですね。
少年時代の私はこの彼女に恋をしてしまったのかもしれません。
一昨年前、作詞活動45周年を迎えられた松本先生の記念ライブにお邪魔させて頂いた話を知人としていた時に、ふとこの曲のことを思い出しました。
最近ではあまり聴くことも無くなっておりますが、黄金の金字塔として自分のなかでは確立されている曲なのです。
今回、この曲をイメージしながらストーリーを書いてみようと思ったのですが、時間は流れあの当時のような感覚では表現出来ませんでした。
でもまあ、なんとなく近い感じはなった気はしますが。
と言う感じで、また文章化にチャレンジしたい曲が思いつきましたら書いてみたいと思います。
今回はこの辺で。
お粗末様でした。












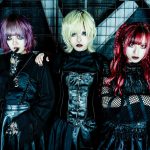












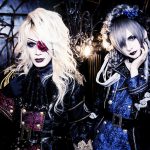



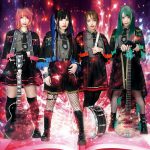





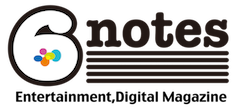
この記事へのコメントはありません。